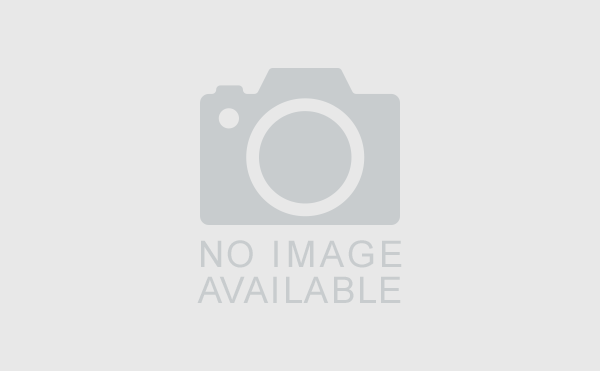【給与計算担当者必見】月の途中での昇給、社会保険料はいつから変える?随時改定の正しい起算月を徹底解説!
「7月15日に社員が昇給。8月25日払いの給与は、昇給前と後で日割り計算したけど…あれ、社会保険料の計算(随時改定)って、8月・9月・10月の給与で見るんだっけ?それとも9月・10月・11月?」
給与計算の実務で、こんな疑問に手が止まってしまった経験はありませんか?
この「起算月」の判断は、担当者の裁量に任されているわけではなく、実は明確なルールが存在します。もし間違えてしまうと、後から保険料の追徴や還付といった面倒な手続きが発生し、従業員からの信頼を損なうことにもなりかねません 。
この記事を読めば、もう大丈夫。日本年金機構の公式見解に基づき、月の途中で昇給があった場合の随時改定(月額変更)の正しい知識と、実務で間違いやすいポイントを分かりやすく解説します。
【結論】随時改定の計算は「昇給後の給与が満額支払われた月」からスタート!
早速、冒頭の疑問にお答えします。
【ケース】
- 賃金:月末締め、翌月25日払い
- 事象:7月15日に昇給
- 8月25日払い給与:7月1日~14日(旧給与)と7月15日~31日(新給与)の日割り計算
この場合、随時改定の算定対象となるのは、「9月、10月、11月に支払われる給与」 です。
なぜなら、社会保険制度には「昇給後の給与が、給与計算期間の1ヶ月分まるまる反映された最初の月から計算を始める」という大原則があるからです 。
8月25日に支払われた給与(7月勤務分)は、新旧の給与が混在した「日割り」の給与です。このようなイレギュラーな月は、昇給後の安定した報酬を正確に反映していないため、計算の土台から除外されるのです。
なぜ日割り計算の月はダメ?社会保険の「1ヶ月満額ルール」とは
随時改定の目的は、昇給などによって恒常的に変わった従業員の報酬を、速やかに社会保険料に反映させることです 。そのためには、計算の基礎となるデータが「安定的」でなければなりません。
- 不安定な月(計算に含めない): 冒頭の例の8月支払給与(7月勤務分)がこれにあたります。日割り計算された給与は、あくまで昇給に伴う一度きりの「過渡的な」金額です。これを計算に含めてしまうと、本来の昇給後の月収よりも低い平均額が算出され、保険料が実態より安くなってしまう可能性があります。これは制度の趣旨に反します 。
- 安定した月(計算に含める): 9月支払給与(8月勤務分)がこれにあたります。この給与は、8月1日から31日まで、昇給後の新しい基本給が初めて「1ヶ月分まるごと」適用されています。このように、変動後の報酬が満額反映された「クリーンな」月こそ、安定した報酬実態を示す信頼できるデータとなるのです 。
社会保険制度は、手続きの速さよりも、保険料計算の基礎となるデータの正確性と信頼性を重視しているのです。
プロはここを見る!日本年金機構の公式見解が答えです
この「1ヶ月満額ルール」は、日本年金機構が公表している「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に明確に記載されています 。
特に重要なのが「随時改定の問6」にある、次の一文です。
「昇給・降給した給与が実績として1ヶ月分確保された月を固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3ヶ月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定の判断を行う。」
つまり、「日割り計算の月は除外して、新しい給与が満額支払われた最初の月から3ヶ月間の給与平均で判断してください」ということです。この公式見解が、私たちの実務における絶対的な拠り所となります。
これだけじゃない!随時改定(月額変更)を行うための「3つの必須条件」
「起算月」のルールを理解したところで、もう一歩踏み込みましょう。随時改定を行うには、実は3つの条件をすべて満たす必要があります 。
- 1.固定的賃金に変動があったこと 基本給の昇給・降給はもちろん、役職手当や通勤手当などの固定手当の変更、時給や日給単価の変更などがこれにあたります 。残業代のような、毎月の実績で変動する「非固定的賃金」だけの増減では対象になりません 。
- 2.変動後の3ヶ月平均で、標準報酬月額が「2等級以上」変わること 起算月から3ヶ月間の給与(残業代など非固定的賃金も含む)の平均額を出し、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があるかを確認します 。
【超重要!見落としがちなワナ】 固定的賃金の変動方向と、給与全体の変動方向が逆になった場合は、対象外です!
- NG例①: 基本給は上がったが、残業が激減して3ヶ月平均の給与総額は下がり、等級が2等級以上ダウンした → 随時改定は行わない 。
- NG例②: 基本給は下がったが、繁忙期で残業が増え3ヶ月平均の給与総額は上がり、等級が2等級以上アップした → 随時改定は行わない 。
- 3.変動後の3ヶ月間、支払基礎日数がすべて「17日以上」であること 計算対象の3ヶ月間、いずれの月も支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)必要です 。1ヶ月でもこの日数を下回ると、随時改定は行えません 。
手続きをマスターしよう!届出から保険料控除までの流れ
3つの条件をすべて満たしたら、速やかに「被保険者報酬月額変更届」を提出します 。
【手続きタイムライン(冒頭の例)】
1.起算月: 9月支払給与
2.算定期間: 9月、10月、11月の3ヶ月間の給与
3.月額変更届の提出: 11月25日の給与が確定したら「速やかに」提出
4.新保険料の適用月: 起算月(9月)から4ヶ月目にあたる12月分の保険料から
5.給与からの控除開始: 「翌月徴収」の会社なら、12月分の新保険料は翌年1月25日支払いの給与から控除開始
「適用月」と「控除月」がズレる点は、従業員へ説明する際にも重要なポイントです。
もう迷わない!まとめと明日から使える実務チェックリスト
月の途中の昇給は、給与計算担当者を悩ませる典型的なケースです。しかし、「昇給後の給与が1ヶ月分満額で反映された月を起算月とする」という原則さえ押さえれば、自信を持って対応できます。
最後に、ミスを防ぐための実務チェックリストをご紹介します。
【随時改定・実務チェックリスト】
□ 固定的賃金の変動か?: 昇給、手当変更など、トリガーとなる事象を確認したか。
□ 起算月は正しいか?: 日割り計算の月を除外し、「1ヶ月満額ルール」で起算月を特定したか 。
□ 支払基礎日数はクリアしているか?: 算定対象の3ヶ月間、すべて17日(または11日)以上あるか 。
□ 2等級以上の差はあるか?: 3ヶ月の平均給与で、2等級以上の差を確認したか 。
□ 変動方向は一致しているか?: 「給与は上がったのに等級はダウン」のような逆転現象が起きていないか 。
社会保険事務の正確さは、企業のコンプライアンスを守り、従業員との信頼を築く上で不可欠です。この記事が、あなたの日々の業務の一助となれば幸いです。